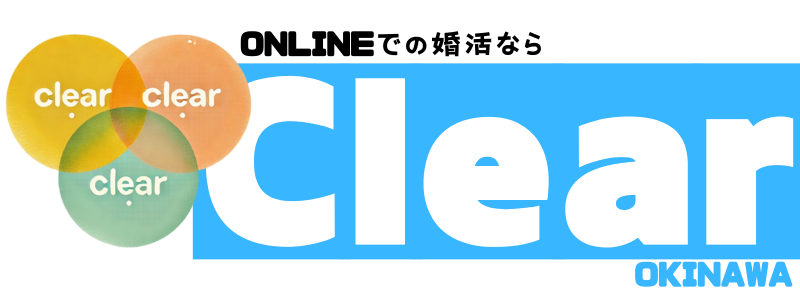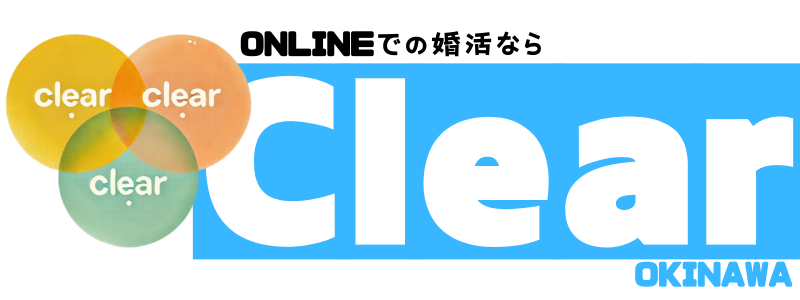最近、東京・東急田園都市線で普通列車と回送列車が衝突・脱線する事故が起きました。
その影響で渋谷〜鷺沼間で運転見合わせが相次ぎ、復旧の見通しも立たず、通勤・通学に大きな混乱が出ています。
事故の原因として、回送列車が所定位置を超えてはみ出して停止していたことなどが指摘されており、非常ブレーキをかけたものの間に合わなかったとの報道もあります。
運輸安全委員会も調査を続けていますが、6日中に調査を終えるのは難しいとの見通しが出ています。
こうした事故が起きると、電車という交通インフラの「安全性」「稼働・維持管理の難しさ」が改めて浮き彫りになります。
沖縄に電車・鉄道がないのはなぜ?背景と制約
ではこうしたリスクを知ったうえで、なぜ沖縄には一般的な電車(鉄軌道)がほとんど存在しないのか、その背景を見てみましょう。
歴史的な経緯と戦争の影響
かつて沖縄には「沖縄県営鉄道」など軽便鉄道が存在していました。
しかし第2次世界大戦(沖縄戦)でこれらの鉄道網は壊滅し、戦後の復旧がなされず廃線になってしまいました。
その後、アメリカ軍統治時代には軍事優先の都市運営がなされ、鉄道復活より道路インフラや基地整備が優先されたという指摘もあります。
経済性・採算性の壁
鉄道を建設し運営するには、膨大な初期投資と維持コストがかかります。
沖縄は都市集中地域が限られており、人口密度が低めであるため、鉄道の「採算が取れる利用者数」を確保するのが難しいとされてきました。
また、地形・都市構造の問題も。沖縄本島は縦に長く、山地や起伏も多いため、効率的なルートを設けにくいという制約もあります。
モノレール「ゆいレール」だけが鉄軌道として残った理由
那覇市内には「ゆいレール」という都市モノレールがありますが、これは比較的短距離区間を結ぶ交通機関で、島全体を網羅する一般鉄道とは性格が異なります。
ゆいレール以外の鉄道導入は構想が何度か持ち上がりましたが、費用や採算性、ルート選定の難しさなどで具体化には至っていません。
事故を知るからこそ、沖縄の「鉄道未実現」の意味が見える
東京で起きた田園都市線の事故を見聞きすると、「鉄道を持つことの重み」が実感できます。
鉄道を運営するには、日々の点検、安全対策、事故対応、修理、人的コスト、信号管理など、多くの責任とリスクが伴います。
そのうえで、沖縄が鉄道を持たない(または限定的にしか持たない)というのは、
ただの“遅れている”ということではなく、現実的なコスト・技術・地理・歴史の積み重ねの結果だと言えるでしょう。
それでも、未来のレールに願いを込めて
沖縄も、交通渋滞や公共交通の限界を抱えている地域です。
鉄道が導入できない現状を変えるためには、技術革新・資金調達・都市計画の見直しが不可欠です。
一方で、今すぐできることとしては、
バスネットワークの整備、BRT (バス高速交通)、公共交通の強化、地下鉄・軽軌道の検討、モノレール延伸などの議論もあります。
ゆいレール以外の鉄道案も、交通需要が増える将来を見据えて、いくつかの構想が報じられています。
まとめ & ClearOKINAWAからの視点
そして、出会いや暮らしを考えるとき、交通利便性もまた大きな要素になります。
移動がしやすい・つながりやすい地域を選びたいという想いも、恋愛や結婚を考える上で自然に浮かぶ視点ではないでしょうか。
ClearOKINAWAは、沖縄に根ざす出会いを大切にしています。
交通や暮らし、地域への想いを共有できるお相手こそ、長く一緒に歩んでいける人かもしれません。